東日本大震災が発生した直後から、東北への支援に尽力されてきた高橋大就さん。「一般社団法人 東の食の会」「NoMAラボ」「驫(ノーマ)の谷」などのプロジェクトを手掛けてきた高橋さんに、事業を始めたきっかけや、移住した浪江町への思い、今後の展望について伺いました。
高橋大就(たかはし・だいじゅ)外務省勤務を経て外資系コンサルティング会社に転職。東日本大震災を契機に東北地方での支援活動を開始。「一般社団法人 東の食の会」を設立し、「Ça va(サヴァ)?缶」のプロデュースなどを通じて、地域の食のブランド化に貢献。現在は浜通り地域を拠点に、まちづくりに取り組む「NoMAラボ」、馬と共生する「驫(ノーマ)の谷」を主宰し、地域創生に取り組んでいる。
原発事故の爆発を見た瞬間、すべての価値観が変わった
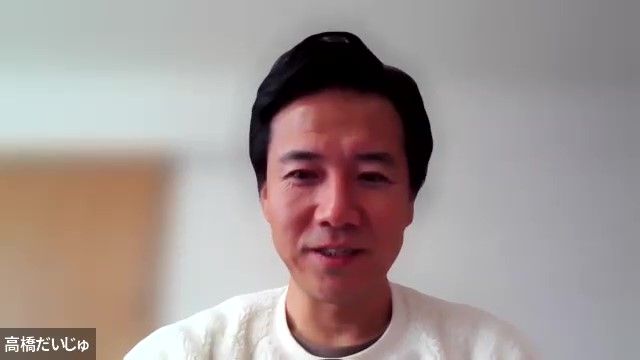
―外務省や大手コンサルティング会社など、さまざまな経歴をお持ちの高橋さんですが、震災復興や地方創生に関わるようになったきっかけを教えてください。
もともとは外務省で安全保障に関する業務を担当していました。アメリカに長く滞在していたのですが、日本に帰ってきたタイミングで、国内経済の疲弊や人口減少について強く危機感を抱いたんです。ずっと外に向けて仕事をしてきたけれど、まずは自分たちの足元が崩れ始めているのを止めなければ……という猛烈な焦りが、新しいキャリアを踏み出すきっかけになりました。
新卒で外務省に入ったので「自分で稼いだことがないのはマズい」「自分の武器を作りたい」と思い、まずは外資系コンサルティング会社に転職しました。3年ほど経験を積んで、自分で事業を立ち上げようと思っていた矢先に、東日本大震災が起こったんです。その後すぐに、東北の食に関する支援を行うために動き出しました。
―被災地に関わる事業を立ち上げる際に、スピード感を持って決断できたのはなぜですか?

画像:一般社団法人NoMAラボ
震災前まで、農業の輸出ビジネスに関する事業を立ち上げるために独立の準備を進めていました。それに加えて、ずっと抱えていたプロジェクトがちょうど終わったタイミングだったことも、「自分がやらなければ」と思わされた理由のひとつです。
震災もそうですが、原発事故のニュースを目の当たりにした時、自分の価値観が大きく変わった実感があります。テレビであの爆発の映像を見た瞬間が、わたしにとって明確なターニングポイントになりましたね。
浪江は“最前線”の町

画像:一般社団法人NoMAラボ
―現在は浪江町在住とのことですが、移住した経緯について詳しく伺えますでしょうか。
震災後、最初は三陸地方で活動していましたが、6年目から福島にフォーカスしました。特に避難指示で入れなかったエリアへの支援が重要だと感じ、浜通り地域に活動の軸を置くことに。その後、本格的に拠点を移すことを決めた2021年当時、最も近づけたのが浪江だったので、浪江への移住に至りました。
それまでの活動では産業再生に力を入れていましたが、コミュニティ再生のほうが時間も手間もかかるんですよね。産業とコミュニティ、両輪でやっていかなければならない、となったとき、コミュニティ再生に本腰を入れるには移住が必要不可欠だと思いました。
―浪江町の魅力を一言でいうなら?
豊かな自然やおいしい食べ物など、魅力はいっぱいあるんですが、一言で表すなら「人」です。ポジティブなエネルギーに満ちた人が多いと思います。逆境の中でも、めげずに立ち上がって一緒にチャレンジングなことができるのは大きな魅力ですね。
浪江は日本の“最前線”。わたしたちは“フロンティア”と呼んでいるんですが、新しい社会システムやコミュニティを自分たちで作っていく場所だと考えています。みんなが当事者意識を持ちながら自律的な社会を目指して一緒に活動できているのは、自分にとってのモチベーションにもなっています。
「楽しい」は原動力になる

画像:一般社団法人NoMAラボ
―移住前から地域の方と関わりながらビジネスを手掛けられていたと思いますが、実際に住んでみて感じたことや、新たな発見などはありましたか?
新しいものを作る前に、地域の歴史や伝統を大切にしたいと強く感じるようになりました。移住者としてこの町に住み始めた際、地域コミュニティの中心的な方から「俺も移住者だよ」と言われたんです。
話を聞いてみると、天明の大飢饉を機に集団で移住してきた人々の末裔なのだそう。移住者を暖かく迎えてくれる理由のひとつとして、もともと浪江には外から人を受け入れる土壌があったんだな、と感じましたね。そういった歴史や、コミュニティの背景を尊重してこそ、新しい挑戦ができるのだと思います。
―地域の方とコミュニケーションを取る中で、印象に残っている出来事があれば教えてください。
“草刈りバトル”を企画した時のことは印象深いですね。空き地になってしまった私有地で雑草が伸び放題になっていたのを課題に感じ、バトル形式で楽しく草刈りをするイベントにしたんです。刈った草でアートを作ったり、草を積んだ高さを競ったり、いろんな楽しみ方ができるようにして。そうしたら、地元の若者からお年寄り、移住者まで多くの人が参加してくれました。いろんな壁を超えて、みんなで一緒に楽しんでいる様子を見た時、自分がやりたいことが凝縮されている景色だなと実感しましたね。

画像:NOMA VALLEY
震災や原発事故で、つらい思いをしたこと、それが今も続いていることは忘れたくないし、忘れられるものではありません。でも、今生活している人たちの喜びや楽しさも大事にしたいんです。復興の先に幸せがあるのではなく、逆なのではないかと。正しくてもツラいことって、なかなか続かないんですよ。現実的な不安や危機感と、ワクワクできるようなエンタメ性を両方抱えながら、どう楽しむか、楽しませるかを考え続けていきたいと思っています。
自分たちの手で“まちづくり”ができるロールモデルに
―高橋さんはこれまでにも様々なビジネスに携わってきたかと思います。特に大切にしていること、意識していることは何でしょうか。
「NoMAラボ」を設立してからは、浜通り地域のコミュニティ再生や新しいビジネスづくりに注力してきました。住民を主体としたまちづくりこそが、自分にとっての大切な軸になっています。
さらに、「自立」を掲げて新たに立ち上げたのが、人と馬と自然が共生する「驫(ノーマ)の谷」です。2024年12月15日にオープンした「ノーマ・ホースヴィレッジ」では、乗馬やホース・トレッキング、ホースセラピーなど馬たちと触れ合う様々なアクティビティを楽しめますよ。ぜひたくさんの方にいらしていただきたいですね。
―今後ビジネスを通して実現したいこと、目指している姿について教えてください。

画像:NOMA VALLEY
抽象的な言い方になりますが、この地域を“めっちゃおもしろい場所”にすることが目標です。国内はもちろん、世界的にも魅力のある地域にして、若い人たちが自己実現しやすい土地にしたいと思っています。
中央集権的なまちづくりではなく、いろいろな人が主体的に自立した関わり方ができるコミュニティを作ることが、結果的に地域の人の幸せにも繋がると思うんです。「驫(ノーマ)の谷」も、その具現化のひとつ。住んでいる人たちが一番楽しくて、一番幸せだと思える地域を作ることが目標です。
―今回のインタビューで、高橋さんの相双地域に対する思いや、“まちづくり”への信念をお聞きすることができました。浪江町の発展と、「驫(ノーマ)の谷」の今後が楽しみです。
連載「情熱の相馬人」では、相馬のこれからを創るさまざまな人の魅力に迫ります。
記事の一覧はこちらから。

